「ハイ、お待ちどおさま」
明るい茶の髪で光をはじきながら、小さな丸椅子に座った幸に飴湯の杯を渡す。愛想を振り向く男に、女は微笑を返した。
明るい日差しの下で、町はまどろみの中にいる。特に主要な場所でもないことから、客はなじみがほとんどだ。そのために、緩んだ気が辺りを覆っている。行き交う人々の会話も、どこかゆったりとしている。 あそこのうち、子供が生まれるってねえ。――これは、刻んで蜂蜜をかけるとおいしいんだよ。――おじさん、これとこれ、どっちの方がいっぱい入ってる? 国境は山であり、そのためか人々の危機感は薄い。
「やー、仕事の途中でこんな美人に会えるなんて僥倖ものだなあ」
「大袈裟ね」
そう言いながらも、満更でもない。あの一行の中にいるとこういった扱いを受けることもないので、余計にそう感じる。古ぼけた茶屋というのが少しばかり不満だが、まあ仕方ないだろう。
「いや、ホントに。ここのところ、美人には会っても美女には縁がなかったからなあ。喰われるのはごめんだが、こうやって付き合ってもらう分にはありがたい」
軽薄な笑顔に口調。そこに投げ込まれた爆弾に、幸は改めて男の様子を探った。良く陽にやけた、バランスのとれた体。明るい色をした、茶色と鳶色の髪と瞳。二十代か三十代か、きわどいところだ。格好は、至って平凡な自由商人の服装。どこにでもいるような、軽薄な商売人だと思っていた。今もその印象は裏切られていない。 だからこそ、誘いに乗ったのだ。さっきの台詞は、言葉通りではなく、ただの比喩だろうか。過剰反応であれば、それで良いのだが。
「ねえ、仕事って何を扱ってるの? その袋の中身、商品なんでしょう?」
「ああ。見るか? 大した物はないが、綺麗な髪飾りなんかは沢山あるぞ。ほら、これなんてどうだ。金色の髪に良く映える」
店先で、商売を始めるかのように色々な物を並べる。緑色の宝石のついたピン、銀細工の髪飾り、紅い宝石の指輪、紋様の彫り込まれた藍い宝石、金細工の腕輪、宝冠、青い指輪・・・。やはり、ただの気のせいだろうか。ところが、何気なく品々を眺めていた幸に、男は次の爆弾を放り込んだ。
「この宝冠は? きっと、瞳とあいまって赤い髪に映えるだろう。まあ、もうつけてるみたいだがな」
この男は、空のことを言っている。
とっさに凝視してしまった幸に、男は相変わらず軽薄に笑いかける。傍から見れば、若い女を相手に口説いているようにしか見えないだろう。しかし幸は、とてもではないがそんな甘い気分にはなれそうもなかった。
「この石は、太陽の光に当たっていると緑だが、他の光では赤く見える。隠している紅い目に、そっくりじゃないか? これは、髪と同じ藍色だな。そしてこれは、血に染まって泣いている、皇子様にぴったりだ」
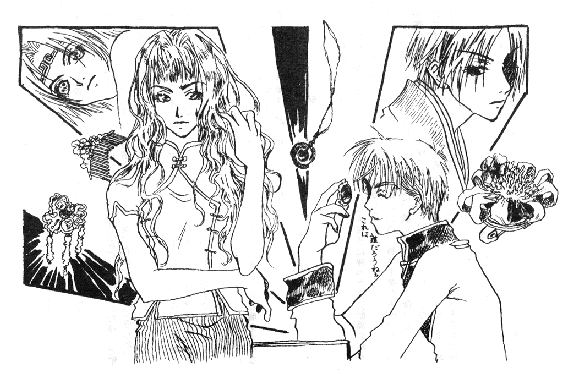
「あんた、何が目的?」
「怒っても綺麗だなあ。警戒しなくたって、別に何もしないさ。それよりも、聞きたくないか?」
男は、幸に笑顔を見せた。ただ瞳だけが、危うげないろをしている。
「皇子様の昔話をさ」
あまりの不味さに、布団を強く握る。大声を上げたりする醜態を演じずに済んでいるのは、和尚の存在のおかげだった。もっとも、感謝する気などあるはずもないのだが。
「良薬は口に苦し、だ」
狸面の和尚は、戻の反応を見てとぼけた声で言った。味が凄まじいために、はっきり言って正真正銘の病人に飲ませて良い代物ではない。だが、効果は確かである。和尚は、律儀に飲み干された湯のみを受け取り、小さく笑った。
「気分はどうだ」
「悪くなった」
「よし、正常だな。これを美味いなんて言ったら、それこそ重症だ」
笑ったまま、戻の頭を軽く叩く。子供にするようなそれに、戻があからさまに機嫌を悪くする。だが和尚は、それを無視して様子を覗った。寝汗でどこかやつれたような感じがあるが、熱は下がったらしく言葉もはっきりとしている。これなら、大丈夫だろう。
「今、水桶を持って来る。体を拭け」
「・・ありがとう」
「ああ、ちゃんと礼が言えるんだな。躾がいい。あとで話がある。着替えてから部屋に来い」
「金なら払えない」
「そうじゃない。それは、掃除をするってことで話がついているからな。話ってのは、妖人のことだ。まあ、この先他の連中と別れて行くなら聞かなくてもいい話かもしれんがな」
しばらくして、戻は和尚と向かい合っていた。病み上がりとは思えない姿勢の良さに、和尚は苦笑した。表情が、意地っ張りめと言っている。だが、戻の姿勢は緩まない。おまけに、射殺しかねない様子で和尚を睨んでいる。
「そんなに睨まなくても良いだろう」
「用件は」
「焦るなって。ところでお前、戌虎[ウェンフー]の異種間論を知っているか?」
「一通りは」
戌虎は、水嵐国の学者だった。彼は、様々な動物を使って異種間の交配についての実験を行った。結果は、種の近いものであれば子孫を残すことも可能であり、種の遠いものは一度の交配には成功しても、誕生する子には生殖能力はないというものだった。つまり、種が大きく違えば、二世代目はいても三世代目以降はいないということになる。
だが、と、和尚は続けた。妖人は三代目以降もいる。
「それに、その数は少なくない。おれは、今妖人って呼ばれている連中の半分とはいかなくても三割くらいはそういった奴等じゃないかと思っている。現に、お前と一緒にいた、藍色の髪の奴は両親共に妖人だ二世代目と三世代目のな」
「・・・見ただけで、判るものなのか」
「いや。ただ俺は、あいつの母親の・・知り合いだ」
「証拠は」
「あいつの母親と知り合いだってことのか?」
「三代目以降がいるということの」
一瞬、和尚の眼が遠くを映す。だがすぐにそれは、穏やかなものに変わる。相変わらずの、狸面だった。
「証拠も何も、おれがそれだ」
戻は、完全な無表情で狸面を睨みつけた。
空が、黄昏色に染まっていた。西の方はまだ青く、東側は徐々に闇が侵食している。星はまだ見えないが、爪で引っ掻いたような細い月は姿を見せている。黙々と堂の床を磨いていた戒は、差し込んだ影に顔を上げた。
「何一人でやってんだよ」
「陸君。お帰りなさい」
「バカじゃねーの」
ぶっきらぼうに言って、無造作に雑巾をひったくる。隣で不器用に床を磨く陸に、戒は微笑を浮かべた。
「ありがとうございます」
「なんでお前が礼言うんだよ」
その言葉に笑いつづける戒に陸が怒鳴って、二人は掃除を再開した。静かだ。空と幸はまだ帰っておらず、戻には一応休んでいるように言っている。ふと、こうやって陸といるのは久しぶりだということに気付いた。
見世物小屋から陸を買い取ってしばらくは、二人で黙って一つの空間を占領していた。あの頃は、陸は今以上に不信感をあらわにしており、一人きりや他の者といっしょにはしておけなかったのだ。妖や妖人を忌み嫌っていた祖父母の近くなど、論外だ。そうなると、必然的に自分の目の届くところに居させるしかなかった。だが、それが不快でなかったことも事実だ。
「なあ。どうして俺を拾ったんだ」
声に振り向いても、陸は背を向けたままだった。
「どうして、でしょうか」
「ただの気まぐれか」
「いえ。・・・そうかもしれませんね。眼が合ってしまいましたから」
「はあ?」
「覚えてませんか? 道で擦れ違った時に、眼が合ったんですよ。もっとも、陸君は僕のことなんて見てませんでしたけどね」
「それ、眼が合ったって言わないだろ」
「いえ、視線は合っていましたよ。君が、僕ではなくて僕が妖人だということを見ていただけで」
妖人である戒が、質のいい服を着て堂々と道を歩いていることに対して。ひどく、傷付いた眼をしていた。それが、陸を引き取ったきっかけだった。一種の一目ボレですかね、と、戒は明るく付け加えた。
「どうしたんですか、突然。今まで一度も訊かなかったじゃないですか」
「いいだろ、どうでも」
陸に応える気がないのを見取って、戒は掃除に専念することにした。訊くようになっただけでも、確実にあの頃よりも良くなっている。
一方陸は、不必要に力を込めて床を磨きながらついさっき聞いたばかりの台詞が頭の中を駆け巡るのを自覚していた。
『僕の唯一の友人だから』
言ったのは、静。漢稀の軍人で、おそらく戻や自分と同じくらいの年齢だ。ぶらついていた森の中で会ったのだ。誰かを探していたようで、何故か陸が戻と一緒にいたと判っていながら、何も仕掛けてこなかった。
戻と知り合いなのか、と訊いた応えがそれだった。大切な人だ、と。
そんな相手と敵対するよう命じられ、どんな気持ちなのか。そんなことを訊くことは出来なかったし、つもりもなかった。ただ、大切だと言い切れる事が不思議に思えた。
「戒は、あいつが一番大切なんだろう」
「今日は、何かあったんですか」
無言の、肯定。何故かそれが悔しいと思いながら、ぼんやりと自分にはそう思える人が出来るだろうかと、考えてしまった。そのことに気付き、慌てて打ち消す。いつの間にこんな風になったのか。失うことが恐いものを作ってしまえば、絶対に弱くなるのに。
聞く人によっては笑い飛ばしてしまうだろう論理が、彼にとっては真実だった。
「暗くなってるっていうのに。二人とも、こんなところで何やってるのよ」
闇の浸食を受けた空の下で、見事な金髪が揺れる。買った大量の荷物を軽々と持ちながら、幸が堂に入って来た。それだけで、わだかまっていた空気が一掃される。
「お帰りなさい、幸ちゃん」
「掃除? そっか、そういう条件だったのよね」
そうは言うものの、手伝う気配はない。わざとらしく、手や肩の筋肉を揉み解しているだけだ。陸は、それを無視することに決めたらしく更に力を込めて床を磨く。彼の持つ雑巾は、酷使されて短い間にぼろぼろになっていた。床も、陸の磨いた狭い範囲だけが、異様に光ってしまっている。
「ねえ。リンレツって名前知ってる?」
「・・・その人が、どうかしたんですか」
思いがけない名前に、戒の視線が鋭くなる。それは、血縁上戻の叔父にあたる人物と同じ名だ。何故、それをここで聞くのか。少なくとも、彼が西端のこの地を治めているという話は聞いていない。
「町で聞いただけよ。誰なの?」
「戻さんの親戚ですよ」
「ってことは、王族?」
幸が、呆れたような表情をした。それがなんだって、小さな町で飴湯を飲んでいるのか。自分達一行のことを知っているのか。即答で断らずに、少しくらいは話を聞けば良かったかもしれない。だが、
「怪しかったし・・・」
「何が?」
「あら、空。どこか行ってたの?」
「うん」
笑顔で応える。その頭上には、すっかり闇色に染まっている空が広がっていた。空は、幸の荷物と雑巾を手に床に座り込んでいる二人を見て、小さく首を傾げた。
「ご飯まだなの?」
三人が揃って苦笑して、その日の掃除は終った。
