疲れた。
ただ、戻と話をしただけだ。それだけなのにこんなに疲れるのは、きっと自分に負い目があるからだろうと、静は思った。
捕縛用に作り変えられた人工オアシス『翠』を後にして、静は仮説テントで一夜を過ごそうとしていた。兵士のものよりは幾分まし、という程度の士官用テントは、殺風景そのものだった。
「変わっていなかったな、戻は」
苦い、自嘲じみた声が零れ落ちる。
この年齢で軍中で出世しようとした静に、初めて出来た友人だった。互いに、良い所をみつけるよりも欠点を挙げる方が早い。それなのに、他の誰といるよりも居心地が良かった。それは、静だけの感情かもしれないのだけれど。
「累。いますか」
「はい、ここに」
静かな声に、テントの外から元気な声が返る。外に出た静は、そこに立っている赤毛の少年に柔らかな視線を向けた。
くせっ毛の赤毛に軽く手を乗せると、信頼のこもった緑の瞳が見上げる。せいぜい十代後半の静よりも、更に年若い少年だ。
「少し、外を散歩してきます。累は寝ていなさい」
ついて行くと言いそうな少年に、釘をさす。何か言たげな、それでも自分の言葉に従おうとする累に言葉だけを残し、歩き去った。
軍の野営地から少し離れたところに、浅黒く日焼けした男が立っていた。二十代後半のその男は、おもむろに自分の着ている、東方の商人が好む生地のたっぷりある服を脱ぐと、持っていた袋から今度は、体にぴったりとした、西方の商人が着ているような服を引っ張り出して着る。
そうして一息ついたところで、近くの茂みが鳴った。それとなく警戒し、構える。出てきたのは、「散歩」に出かけた静だった。
「こんなところで何をしているのですか」
「静ちゃんか。驚かすなよ。俺、こう見えても気が小さいんだぜ」
「それは意外ですね」
「だろ?」
冷ややかな静の言葉に動じることも無く、飄々と言葉を返す。表面はくつろいでいるのに、実際には、何が起きても対応できるように構えている。
「それで、どうしてここにいるのですか、炎王」
辛辣に言った静の言葉に、烈が顔をしかめる。名前だけのこの位にはウンザリしている。
先帝の弟であり、現皇帝の叔父にあたる烈は、不在と気紛れで有名だった。
「そんなつれない言い方をするなよ。俺と静ちゃんの仲だろう?」
「貴方と親しくした覚えはありません」
「また、そう言うことを言う。上官には媚びを売っとくもんだぜ」
「先のない上官に取り入ってどうするのですか」
「厳しいなあ」
苦笑いをする。
烈にしてみれば、表層だけのおべっかを言う者よりも、よっぽど静のような者の方が気が楽だ。その方が、信用も出来る。もっとも烈が、知られて困ることを誰かに言うことはまず無いのだが。
「話を戻します。どうして、こんなところにいるのですか。貴方は犀樋地区にいるはずでしょう」
東南の地域名を挙げる。そこは、安定した、今のところさしたる危険も重要性も無いところだった。
きっと俺には、粛清の口実さえ望んでいないだろう。
無気力に、ただ比較的少量の金を食い潰すだけの叔父よりもむしろ、弟や他の精力的な父親の兄弟に対抗意識を燃やしていることだろう。烈の兄弟は多く、彼より年少の者もいるために、現皇帝の昌と同じ年齢の兄弟もいる。
「あそこは退屈だから、蓮に任せて来た」
気の毒な補佐官は、この頃諦めの境地に陥っている。それでも、烈の顔を見ると小言が尽きることなく溢れ出るのだった。烈はそんな蓮が、嫌いではない。ただ、苦労をかけないよう努力するほど「良い人」でもないだけで。
「わざわざ商人の振りをして、ですか」
「よく判ったな。と言いたいところだが、この格好を見りゃ分かるか」
「町で貴方を見かけました。あの五人のことを探っていたでしょう」
「ああ。面白そうだったから」
悪びれることなく言うと、静の肩に手を置いた。まるで親しい友人にするかのように、軽く叩く。
「もう寝る時間だ。俺なら気にするな。お前さんの邪魔はしないさ、柳静」
立場上、呼び捨てにされても文句は言えない。不快げに眉をひそめた静を無視して、半ば強引に戻らせる。今夜は何も得られないと判断したのか、案外素直に去って行った。
「結果的に、昌の邪魔はするだろうがな」
皇帝になったことで「琳輝鐘」となった皇帝の旧名を、増して呼び捨てにしたことで、不敬罪で捕らえられてもおかしくない。だが、人気の無い夜の森では、誰かに告げる者もいない。
「凝った王朝の血なんざ、途絶えれば良い。大切な者も護れない、こんな身分なんて。なあ、 」
呟いた名が、空中に散る。
ただ、闇の奥から星の燈だけが見つめていた。
「お帰り」
「・・・うるせェ」
一人抜け出した陸を、焚き火から離れたところで幸が迎える。どうやっても森の外に出られなかった陸は、機嫌が悪かった。情けなくもある。
「あんた、一人で出て行くつもりだったんでしょ。馬鹿ねえ。空が言ってたじゃない。ここは檻だって」
「・・んだよ。ここでずっと暮らすのかよ。俺は嫌だぜ」
「あたしだって嫌よ。じゃなくて、あんた一人で出て行くなんて無理だって言ってるのよ。馬鹿なんだから」
逆上して飛びかかる陸を、幸が軽くかわす。そのまま木に激突したのを、嘲るでも哀れむでもなく、碧眼が見つめる。
「ち・・くしょ・・・」
「そういうとこ、馬鹿だって言うのよ。わかってるんでしょ。ガラじゃないんだから、こんなことさせないでよね」
「頼んでねーよ」
ふてくされた声に、幸は溜息をついた。まるで子供の相手をしているようだ。それが懐かしい気がするのは、何故だろう。
「いちいち戻に突っかかることないでしょ」
「悪かったよ、俺なんかが団欒ムード壊して。だから出てくって言ってんだろ」
強く言った言葉が、幸の瞳に吸い込まれて消える。静かな空気の中で、幸の「馬鹿」という言葉が聞こえた。
「陸。あんた、戻と比べすぎよ。あたしたちは、戻がもう一人欲しいわけじゃないわよ。陸は陸で、いて欲しいのは、そんなことにも気付いてない、馬鹿なままのあんたなんだから」
そして、二人同時に顔を背ける。暗いからそうはっきりと見えるわけではないのだが、向かい合っているのが気恥ずかしかった。
「あたし、寝るわ。あんたも早く寝なさいよ」
幸が踵を返して、早足で焚き火へと去って行く。陸は、黙ってそれを見ていた。
「お節介、だよな・・」
満天の星が広がっている。明け方になるまで月は出てこないので、星明りだけが頼りだ。その光と闇の下で、戻が一人、夜空を見上げていた。幼い頃から、気付けば空を見ていた気がする。空と采と、それだけを見ていても良かった頃。
あの頃から自分に何か変化があったのか、よく判らない。外面だけは誤魔化せるようになっても、何も変わっていないとも思う。今も、全て投げ出して采のいる家に帰れたらどんなに良いかと。出来もしないことを考えてしまう。
「強くなる、か」
誰にも言わず、だが、自分にだけは明言してきた約束。数少ない「護りたいもの」を、これ以上失わないように。
一方、そこから少し離れたところでは、戒が焚き火を見つめている。幸がこの場を離れ、陸が森をさまよっていた頃だ。焚き火の近くには、戒だけしかいない。熟睡しているはずの空までもが、どこかへ行っている。
だが、戒はその事を気にしてはいなかった。この「森」に危険があるとも思えなかったし、それよりも、昔の記憶が頭を占めていた。
「僕は、あの時誓ったから。僕が本当に生き始めたのは、あの時からなんですよ、戻さん・・・」
「戒」
「・・・空ちゃん? 何処に行ってたんですか?」
闇の中に、黄金の瞳が光っている。それは、気紛れな猫を思わせた。その瞳の中で、反射した炎が踊る。
「戒は、本当に戻が好きなんだね」
「語弊が、あると思いますが・・・好きですよ。何しろ、僕に命をくれた人ですから」
にっこりと、空が微笑む。それは、「いつも」の空ではなかった。落ち着いた、鋭い雰囲気を持っている。あの軍人が来たときと同じだが、あのときのように虚ろではない。
「よかったね、一緒にいられて」
「・・・・はい」
「あ!」
不意に上を見上げ、声を上げた。つられて、戒も見上げる。その先には、幾筋もの光がはしっている。
「星が落ちていく・・・・」
「久しぶりだな、大きな流星群なんて。やっぱりキレイだな―」
古来、流れ星は凶兆とされる。その象徴は様々であり、地震のような天災や飢餓、大火事などの誰もに影響のあるものから、王位交代といった一般人には実感し難いものまである。
「何か天災が、起こるのでしょうか」
それとも。帝位交代の、兆しだろうか。
そんなことを考えている戒の近くで、空がくすりと笑う。清らかな、巫女かのように。
「本来事象に意味はないよ。意味を持つのは、誰かがそれを認めるからだ。肯定にしろ否定にしろ、誰かが存在を認めてようやく、事象が意味を持つ。だからどうせなら、実現して欲しい方を認めたら良いよ。その通りになるとは限らないけどね」
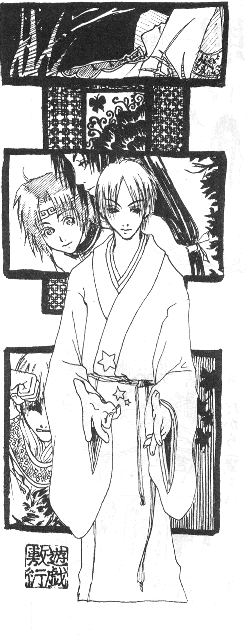
「・・・・そうですね」
嫌味ではなく自然に、空が笑う。
「キレイだね、流れ星」
「はい」
途切れることなく描かれ続ける星の軌跡を、戻が、幸が、陸が、見つめている。あるいは黙然と、あるいは呆然と。そして、そこから離れた彼らに敵対する者たちも、流れる星を見上げていた。
烈と別れて幕舎に戻った静が、まだ起きていた累と共にそれを目にし、わずかに眉をひそめる。草の上に寝転んだ烈が、そのままの体勢で口笛を吹く。彼らが空の言葉を聞いたならば、どう思っただろうか。
そして、遠く離れた漢稀国帝都・央楼では、「皇帝」が空を見上げ、拳を握り締めていた。
「運命の通りになんて生きてやらない・・・・この国は。俺のものだ・・・! 誰にも、渡すものか・・・・」
星は誰とも無関係に、ただ、流れている。
