犬猫が辺りを呑気に走り回っている。質の良い服に身を包んだ人々の表情が明るい。帝都ほどではないにしても、賑やかな町だ。そんな中を、炎色の頭がせわしなく動いていた。
彼女がこんなに大人数を見るのは初めてかもしれない。一緒に暮らしていた山賊たちも大所帯ではあったが、それでもせいぜい一村程度だった。増して、今日は祭日だ。掃き捨てたくなる程の人が集まっている。
「これは、厄介なときに来たな」
「え? どうして? みんな、オマツリだって言ってるよ。オマツリって、楽しいんでしょ? みんなで騒いで、お菓子食べたりお酒飲んだりするって言ってたよ」
「ちょっと待ちなさいよ! あたしは荷物もってるんだからっ」
立っているだけでも人目をひく三人が一箇所に集まった上に騒いでいれば、嫌でも人目を集める。ようやくそのことに気付いた戻が、舌打ちをして「人間の一般常識」の欠如している二人の連れを一睨みした。
「どうでもいいからとっとと歩け。俺は見世物になるのは御免だ」
「じゃあ荷物持ってよ。そしたら大人しくしてあげるから」
「じゃんけんに負けた奴が持つ、と決めたはずだが」
「だってこんなの初めてなのよ。手加減くらいしなさいよっ・・・って、聞いてるのっ?」
真っ先に反応するはずの空が無言なのを訝しく思い、いるべき場所に目をやると、そこにはどこかから迷い込んだ小猿がいるだけだった。一瞬、空がそれに化けたかという馬鹿げたことを考えたが、そんな穏やかなものではなかった。
「そんなの知らないよ、そっちがぶつかってきたんじゃないか」
「なんだと!」
威勢の良い声とドスのきいた声の方を見るまでもなく、ご丁寧にも事情説明を買って出た者がいた。下心とも言えない目論見を抱いて、安っぽい尊大さを撒き散らしながら。
「あちらは、あなたのお連れさんですよねぇ。人にぶつかっておきながら謝りもしないなんて、躾がなってないんじゃないですか?」
「あーあ、天を怒らしちまって。ほっとくと、大怪我をするぜ」
近頃見なくなったような脅しに、戻は酷薄な笑みを浮かべた。幸は幸で、うんざりとした様子を隠そうともしない。
だらしなく服を着崩した男たちは、思わしくない二人のすぐに上辺の仮面を脱ぎ捨てた。人の少なくなった通りを振り返り、天という男に叫ぶ。天は、緑の髪をした巨体の妖人だった。
「おい天、やっちまえ。よく見とけよ。次はお前の番だからな」
「ねえちゃんは、こっちに来な。悪いようにはしねえよ」
男が、下品な笑みを浮かべた。が。
「あんたたち、ばっかじゃない?」
男たちの笑いが止んだ。人によれば、それだけで身動きが取れなくなるような凶悪なかおを向けても、幸は平然としている。
「あんな奴に空が負けるわけがないじゃない。知らないって、滑稽よね」
「なに・・・」
いきり立った男たちは、ありきたりの台詞を最後まで言うこともなく、地に沈んだ。どうやったのかはわからないが、少し離れたところに立っている戻が、何かしたらしい。彼は、相変わらず悠然と立っている。
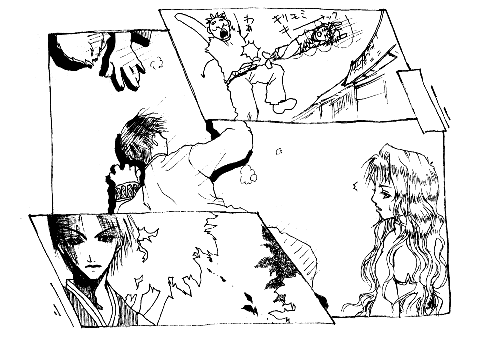
「あれくらい、あたしでも大丈夫だったのに」
「知るか。鬱陶しい戯言は聞き飽きた」
幸は、無言で肩をすくめた。さっきの素早い攻撃に、もしかしたらあたしより強いのかもしれない、との念を抱く。その間に、空の方も決着がついていた。
「凄かったなあ、あのボウズたち」
「でも、赤い髪の奴は妖人だろ。だったら・・・」
「バカか。相手もだぞ」
「それもそうか。強いな、あいつ」
書生風の若い二人組の男が、そんなことを話しながら歩いている。緑頭の天を筆頭に手に余る者達だっただけに、噂が広まるのも早かった。そして、そのほとんどが好意的なものだ。
祭りの半ば開放的な空気のせいもあるが、元来大きな町というものは様様なものを受け入れる性質がある。妖人さえも、ここでは「居る」ことを許される。居心地がいいかどうかは別だが、場所によっては存在する事さえ認められないこともある。
そんな町の中で、「危害を加える妖人」をのした三人組は、一応の居場所を得たことになる。
「で、連れていった奴は何者なんだ?」
身なりの良い若者が恐れ気もなくあの三人組に近付いたときには、陰で成り行きを見ていた人々が、思わず息を呑んだ。緑髪の男のように、投げ飛ばされると思ったのだ。そうなれば、常人が、増してあんな痩せた色男が、生きている保証はない。だが、そうはならなかった。その顔を見て、幾人かが納得したような、感心したような声をも漏らした。
「やけに親しげに話していたな。知り合いなのかな?」
突然話に割り込まれ、二人はぎょっとした。見れば、東方の商人が好む服を着た、三十くらいの男が立っている。その陽にやけた褐色の肌と飄々とした雰囲気から、二人は男を話好きな商人と判断し、安堵の息を吐いた。
「なんだ、驚かすなよ。軍の奴かと思ったじゃないか」
「悪ぃ悪ぃ。しっかし、なんだってこの町の奴らは、こんなにびくついてるんだ?」
町中が浮かれているようでいて、その裏では何かに怯えている。そのことに、男は気付いているのだ。男の明るい茶の髪が、風に掻きまわされた。
髪の短い男が、周りに目を配りながら言う。
「ここに来る途中に見なかったか? 今、ここら辺を国軍の奴等がうろついてるんだよ。何の説明もなしに、な。気にするなって言う方が無理ってもんだ」
「なに考えてんだか、俺らにゃさっぱりだ」
「ふうん。ひょっとして、王族の誰かがお忍びで来てるのかもな。で、そのままとんずらしたとか。あの三人組の金髪の女なんて、どうだ?」
「まさか。言っちゃなんだが、気品なんてなかったぜ。金持ちの妾がいいとこだ」
そんなことを言う長い髪の男に一瞬だけ酷薄な視線が投げかけられたが、それは、気付かれることなく軽薄な笑みに打ち消された。
「話を戻すけど、あの三人を連れて行った男は何者なんだ? この辺りの奴か?」
「ああ、あいつか。あんた、この町初めてだろ」
「まあ、そうかな」
「だろうな。ここらじゃ有名だぜ。妖人の当主って言やな」
「悪いな、戒。こんなものまで連れて来て」
「構いませんよ。賑やかになりましたし」
「騒々しいの間違いだろう」
あっさりと言い放った戻の横では、長い黒髪を束ねた青年が曖昧な笑顔で座っている。空と幸に、その言葉が聞こえなかったのは幸いだった。
そんなことを言われているとは知らない二人は、部屋の中を物珍しげに見て回っていた。大きな商家である戒の屋敷には、今までに二人が見たことがないものが山程あるのだ。この部屋にあるものだけでも、見ていて飽きない。不意に、青い指輪の前で、二人は揃って首を傾げた。
「その指輪が気に入りましたか?」
優しく問われ、二人が振り向く。二人とも、何かを思い出すような表情をしている。
「違うの。あたし、この指輪に見覚えがあるのよ。でも、どこで見たのか思い出せなくて・・・」
「あたしも。おっちゃんたちのとこは違うし。どこで見たんだろう」
「何処にでもあるものなのか?」
「さあ・・・。あれは、父の指輪です。母は、貰っただけですから」
戒の父は、妖だった。高い知能と優れた変身能力を持っていたらしく、ほとんど人間と見分けがつかなかった。人の中での生活を好み、主に詐欺をして生活していたらしいのだが、それは、戒の母・麗
明
そんな矢先に、一人の道士が店を訪れ、食べ物を乞うた。若い夫婦は、快くその道士に食事を与えた。そして道士はその礼に、彼の本性を暴き、「退治」してしまったのだ。
麗は、ショックを受けながらも、一人の子供を産んだ。その子供の瞳は赤かった。麗の両親は執拗に戒を排除しようとしたが、彼は生き残り、たった一人の孫だったために、店を継いだ。
戒にとって、味方は母しかいなかった。その母も今はおらず、祖父母は残った。だが、今は母以外の味方もいる。それが、戒を支えていた。
「そうか」
幸のときと同じ応え。
それに対して、戒はにこりと微笑んだ。聞いた事に詫びるような相手であれば、こんな話はしない。目を背けて欲しいわけではないのだから。
「食事にしましょうか。そうそう、会って欲しい人がいるんですよ」
言いながら、三人を案内する。優しさと素っ気無さの対極ながらともに美形の二人と、直接的な美人の幸、少年のような空も含め、見栄えの良い四人を見た使用人達が、うっとりと溜息をつき、あるいは小声で歓声をあげる。慣れている戻や戒、幸は気にも止めないが、こんな反応は初めての空が不思議そうに彼女達を見ると、更に歓声が高まった。
驚き、思わず身を引くと、丁度部屋から出てきた人にぶつかった。相手が、短く悲鳴をあげる。
「ごめんなさい! 大丈夫?」
慌てて、手をとって起き上がらせる。相手は、質の良い服を着た、十代後半くらいの少女だった。肩までの髪は、瞳と同じ亜麻色をしている。
「ありがとう、大丈夫よ。あなた、兄様のお客様?」
「え? えーと・・・・戻がそうなら、多分、そうだと思う」
「だったらこっちの部屋よ。みんなとはぐれたんでしょ?」
気付けば、他の三人がいない。後ろにいたため、気付かれずに置いて行かれたらしい。部屋に行くと、丁度戒が空を探しに行くところだった。
「兄様、お客様をお連れしました」
「気付かずにいてすみません、空ちゃん」
「違うよ。あたしが遅れたんだから、だから、あたしこそごめん」
「無事だったんだから、どうでも良いじゃない」
「それでは、失礼します」
「鈴
