さびれた田舎の村だった。覇気のない素朴な村の広場には、今や村中の人が押しかけていた。大人も子供も、誰もが異様に残忍な瞳を光らせている。だが、そのことに気付く者はほとんどいない。
その例外のうちの一人が、人々が注視している、言わば主役の片割れだった。つややかな髪と瞳は、同世代の若者と比べてかなりほっそりとした体躯とあいまって、まるで都の女形のようだった。その、端正な顔が人々に向けられる。
「これですね?」
彼の足元に転がされた、もう一人の主役を指し示す。それは、両手を後ろ手に縛られ、汚れ、くすんだ赤髪を直に地につけ、黄金色の双眸を大きく見開いていた。
傷つけられ、熱い砂に焼かれた肌はかなりの苦痛を伴うはずだが、取り囲む人々の誰一人としてそのことを気にする者はいなかった。むしろ、細身の少年の言葉に乗じ、野次を飛ばす。
彼は、赤毛のそれを退治するよう頼まれていた。「数年前に捕らえ、何も食べさせてもいないのに生きている」と、村長は気味悪げに言った。このあたりに役人などが来ることは滅多になく、嘆願状は簡単に無視されてしまう。だから、『誰か』を待っていた。
どうやって生き永らえているのかは判らないが、殺せないほどに頑強というわけではない。現に、村の若者たちは幾度も暴行を加え、怪我を負わせている。ただ、止めを刺す勇気がないのだ。あるかもしれない『何か』を恐れ、手を下せずにいる。
そこへ訪れた道士を、たとえ年少といえども彼らが見逃すはずがなかった。そして今、娯楽の少ない村人たちは、これから起こるだろうことに期待を寄せていた。その思いが、どれほど人としておぞましいかも知らずに。
だが、それは裏切られた。
黒髪の少年は、袂から取り出した金色の輪をくすんだ赤髪に嵌め、涼やかに人々を見た。
「これを私にくださいませんか。丁度、旅の護衛の者が欲しかったので」
「だめだ! そいつがここへ戻ってきたらどうする!」
「そうだ! この町は終りだ」
「あたしたちはあんたみたいに逃げればいいんじゃないんだよ!」
「早くそいつを殺せ!」
延々と続くと思われたそれは、少年の凛とした声と咆哮めいた悲鳴に遮られた。少しして、誰もが凝視する中、少年が口を閉じる。と同時に、赤髪のそれがぐったりと身を横たえた。人々が視線を交錯させ、騒ぎ出す一歩手前で少年が総白髪の老人に声をかけた。
「あの輪を嵌めていれば、僕には逆らえません。獣は痛みに敏感ですからね。この村を襲うことはないと、僕が保証します」
人々は、少年に威厳を感じた。誰一人として、その言に逆らえる者はいない。せいぜい十六、七の少年道士に、畏敬の念を抱く。
「是非、我が家においでください」
村長が「化物」を連れて行くことを認めたばかりか、そんな言葉をもらしたのは、それへの本能的な絶対敬服のためだった。
「お前、何故あんなところにいたんだ」
戻は、闇に囲まれた森の中で、さほど関心がなさそうに尋ねた。
尋ねられた方は、慌てて口の中のものを飲み込み、一瞬、何かを思い出すかのように目を伏せたが、すぐに少年の闇色の瞳を見た。その様子には、出会ったばかりの戻を警戒するような素振りはなかった。
あの後二人は、遠慮なくもてなしを受けたものの、食事と少女の身支度を終えると、すぐに村を出た。だから今、村を見下ろす位置にあるこの森にいるのだ。焚火の周りにのみ光の存在するこの場所に。
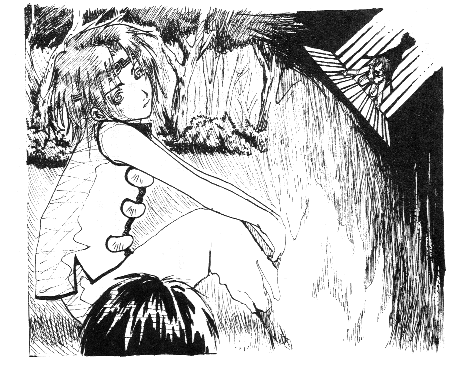
「おっちゃんたちがいなくなって・・・だから、一人になっちゃったから、村に行ったんだ。でも、閉じ込められた。誰も、話もしてくれなかった。おっちゃんたちとは、全然違った」
「おっちゃん?」
「えっと・・・山賊、してた。みんな、いい人だよ。楽しかった。でも、きっと・・・もう会えない」
少年は息を吐き、汚れが落ちて鮮やかになった火色の髪を見た。その頭には、まだ金輪が嵌められている。
「おい、お前。生きていたいならもう人のいるところに出てくるな。この山の奥ででも人目につかないようにして暮らせ」
この時代、人々には恐れの対象が山ほどあった。何もかもを孕む夜が、闇が恐ろしい。獰猛な獣が恐ろしい。ろくに太刀打ちできない病気、災害が恐ろしい・・・・。妖人も、そんな恐怖のうちの一つだ。
妖人とは、妖
「どうして?」
よく磨かれた金貨のような――稀にある「人間」の金色の瞳とは比べ物にならないくらいに鮮やかな 瞳が、なんの躊躇いもなく真っ直ぐに少年に向けられる。
「ねえ、どうして?」
「人のいるところにいれば、この先も昨日のようなことが繰り返される。だから、人前に出ないほうが幸せだ」
自分が信じてはいないことを、戻は口にした。それは、彼であれば絶対に選ばない選択肢。だが。何年もの間村人たちの仕打ちに甘んじていた者が、自分と同じ途
「いやだ」
それは、瞳の光と同じ真っ直ぐな声。
「独りでいるのは嫌だ。おっちゃんたちがいてくれたから、ムカシには戻れないよ。それに」
僅かに強張り、大人びていたかおが、何の打算もない無邪気なものに戻る。
「あたしをゴエイにしたいって言ったよ?」
「・・・・・・・は?」
「言ったよ。だから、どこかに出かけるんだと思ってた。違うの?」
不思議そうに覗き込む少女・・・女の子に、戻は呆気にとられた。確かにあのとき、彼はこの子――そのときは、男だと思っていたのだが――を助けた。金輪を嵌めるときに声をかけ、呪文に合わせて苦しむという猿芝居をさせたのだ。それは、彼の気まぐれによるものだった。あまりに他人
はじめから、彼女を伴って旅をするつもりなどなかった。持っている能力も使わない妖人は、人の目を集めるだけのお荷物でしかない。戻は、そう思っていた。
だが、気が変わった。
放っておけば「嘘をついちゃ駄目なんだよ」とでも言い出しそうな彼女に、気を削がれたのかもしれない。
「お前、名は?」
「空
「空。俺は戻だ。瞬戻。姓が瞬、名が戻」
「シュンレイ・・・・レイ?」
「明日にはここを出る。ついて来れないようなら、置いて行くぞ」
「うん!」
「早く寝ろ」
空の弾むような笑顔が、見なくても判った。戻は、術のために消えることのない炎を背に、目を瞑った。
翌朝、手早く朝食を済ませると、すぐに歩き始めた。道すがら、何年もしゃべっていない反動なのか、空はひたすら話し続けていた。戻の荷物を細い肩に担ぎながらも、疲れている様子はない。
そんな調子で半日近く歩き、森の中に入っていった。そこに朽ち果てた小屋を見つけ、空が駆けて行く。どうやらここが住家だったらしいと察し、戻も歩みを止める。だが、小屋に入ろうとはしなかった。
他人の過去まで背負うつもりは、無い。
例え、小屋の中がどんなに荒れていたとしても、逆に、変わらないように見えたとしても、それは彼女の問題でしかない。知ったかぶりをして口を挟み、相手も自分も傷付けるなど、馬鹿げている。
しばらくして空が小屋から出て来ると、そこに戻の姿は無かった。荷物は全て自分が持っているのだから、一人で行ったはずはないとは、考え付かない。ただ、不安で。恐くて。
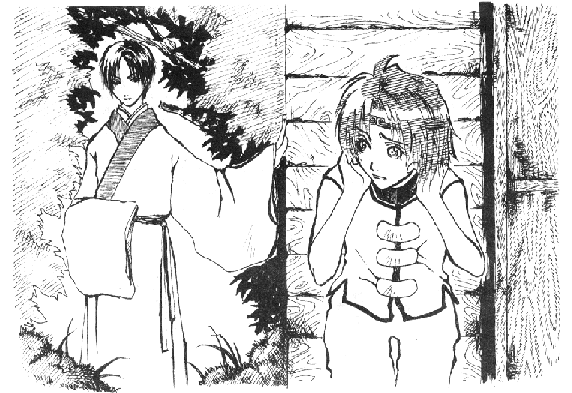
「レイ? レイっ、どこ・・・」
「呼んだか」
小屋の近くの木陰から、戻が姿を現した。無愛想に、素っ気無い台詞を口にする。だが、空にはそれで十分だった。誰かが自分の声に返事を返してくれる。それだけで。
あの村で過ごした数年は、自覚の無いままに、確実に跡を残していた。
「どこに行ってたの? ・・・置いてかれたかと、思った」
「慌てるな。とりあえず置いていくつもりは無い。それよりも、空、お前今元気か?」
「え? う、うん」
きょとんとしたかおで見返す空に、戻はついて来るように言った。
「多分、見ておいた方が良いものだ」
それだけ言って踵を返す戻を、慌てて追う。木の無い、人が四・五人はくつろげる場所に出て、ようやく戻は立ち止まった。そこには、大きな獣の骨が散乱していた。
空は、それに見覚えがあった。はっきりとではない。だが確実に、自分はこれを知っている。
「これ・・・?」
「ああ。これが、お前が今まで何も与えられずに生きてこられた理由だ」
戻は、そこで言葉を切った。無表情ながらも、少しばかり迷っているようでもあった。じっと、空がその瞳を見つめる。
「・・・名は忘れたが、飲み食いがなくても生かせる術がある。誰にでも、呪文を唱えなくてもできるから、正確には術ではないのかも知れないがな。ただ、術をかける相手を強くおもい、その身に付けていた物を持って何かに自分を食わせれば良い」
必要なのは、相手の身に付けていた物以外には、意思の強さと術者本人のみ。生きながら食われることに耐え、対象をおもいつづける強さ。並大抵のことではない。そして、あまりに凄絶だ。それ故、禁じる必要も無い「術」。
「有効期間は、一年。恐らく、一年ごとに行っていたんだろう。こいつらが自ら進んで、な」
この術を強いることはできない。考えてみれば、当然のことだ。激しい苦痛の中でそれ以外のことを考えるなど、強要されたからといってできるものではない。
空は、散らばった骨を凝視した。様々な種族が混ざっている。近くには、すっかり色褪せた自分の服の切れ端があった。昔、この森の動物と遊んでいて破られたものだった。
「どうして・・・? だって、あたしなんにもしてないのに。みんなの事だって、考えてなんて・・・・」
「それだけ、ここの奴等にとってお前が大切だったという事だろう」
それだけ言って、戻はその場を離れた。
空は、ここに残るかもしれない。膝を抱え、歩き出せないままに。または、残った動物立ちと過ごすために。そうなれば、戻は今まで通りに一人で旅を続ける。むしろ、双方にとってもその方が良いのかもしれない。
ひとをあまり近付けないのは、戻の弱さであり、防衛手段でもあった。
「全く、とんでもない奴だな」
自分が度し難い事を知っている。それでも、変えるつもりは無かった。気まぐれに助けた少女に、少なからず執着している事までは意外だったが。
今は、待つしかできない。
「戻、おなかすいたよ。御飯にしようよ」
夕暮れになって戻ってきた空は、軽く目を瞑っていた戻を揺さ振った。戻が、不機嫌そうに目を開く。
「遅い。昼飯もまだなんだぞ」
「食べてれば良かったのに」
「食料は全部お前が持っていっただろう」
「あ。ほんとだ」
空腹を感じるということは、骨を埋めて来たのだろう。埋葬してしまえば、術は解ける。だが、二人ともそのことは口にしなかった。
「ねえ、早く食べようよ」
「・・・うるさい」
群青色の夏空の下で、荷を広げる二人。その向こうでは、動物達の哀しげな鳴き声が聞こえる。
