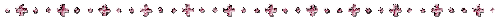
【サンタクロウス】 一般的には、赤髪の子供の姿をしているといわれる。他の妖精のようにいたずら好きでもものをよく隠すが、その姿を見た者には幸運を授けてくれる。煙突を好み、特にクリスマス前夜に見られる。一部地域では、老人の姿をしているとも伝えられる。(世界俗説辞典・栄楽社)
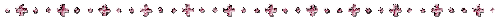
東塔からは、聖夜祭のにぎやかなざわめきが聞こえてくる。逆に、学生寮となっている西塔は、すっかり静まり返っている・・・はずだった。
「なあなあ、ホントに見えると思う?」
「言うなら、『いると思う』じゃないんですか」
「だよなあ。巽ってガキだから」
「なんだよ、年一緒だろ!」
三種類の言語が、テンポ良く飛び交う。
「国」という概念が薄れて久しいが、この学園では、それが極まりつつも、個々を大切にしていた。他に例を見ないほどに様々な民族が共に生活しているが、共通言語の押しつけはない。代わりに、幼少時からの言語教育の為、ほとんどの生徒がいくつもの言語を自在に話せ、そうでなくても聞き取りはできる。
そういった環境のため、一年でも特に盛り上がる聖夜祭をすっぽかして寮に残った3人組は、それぞれの母国語――といっても、彼らはその母国を、知識としてしか知らないが――で喋っているのだった。
「そういうこと言ってんじゃないってーの」
金に近い茶の髪と深い緑の目をしたルイス・エンデが、身を乗り出して抗議してきた水無瀬巽を見下ろす。三人のうちではルイスが一番背が高く、十センチほど置いて、他の二人が並ぶ。
「そうですよ。巽、ルイスは年齢を問題にしてるわけではありません」
笑いながら巽の頭を、子供にするように軽く叩くのは、楊明月 [ヤンミンユエ] 。髪も瞳も巽と同じ黒だが、巽よりはいささか赤みがかっている。縁付きの眼鏡は常にかけているものだが、視力矯正手術の盛んな昨今では、ごく少数派だ。
「じゃあ何なんだよ?」 、
「お前は、精神的に子供だって言ってんの」
「どこが!」
「具体例その一。真夏にアイスの食べ過ぎで腹を壊した。今時、幼児でさえやらないボケだぜ」
「具体例その二。大雪が降った日に、機能麻痺している町や学校をものともせず、寒い中を嬉しそうに走り回っていた。貴重なほどに無邪気ですね」
「具体例その三」
「もういいッ」
ルイスと明月に二人がかりで証言され、むくれる巽。明月はよほど、その様子が子供っぽいのだと言おうかと思ったが、言いはしなかった。断然、今のほうが面白いし、羨ましいのだから。
巽は、座って頬を膨らませたまま、立っている二人を睨みつけた。
「お前らが老けてるんだよ。どっかのサギ師と学者みたいで」
学内でも有名人の二人は顔を見合わせ、噴き出した。互いに、「ぴったりだぜ」「絶対になれますよ」などと言い合っている。巽さえも、膨れ面をやめて、笑っている。
どんな言葉が飛び交おうと、そこに悪意はなかった。
この学園の寮は、無作為なコンピューターの選別で同室者を決められる。当初、正反対のルイス・エンデと楊明月は、それぞれが異なった方向での好成績者だったために、その同室を危ぶんだ教師もいたが、元々気が合ったのか、それとも巽が緩和剤になったのか、とにかく上手くやっている。上手く行きすぎて、結託して何かとやらかす三人に、今度は別の意味で頭を悩ませる羽目になったのだった。
そして今、校内きっての問題児の彼らは、本来ならば明け方まで騒ぎ通す聖夜祭を自主欠席し、暗い寮でサンタクロウスを待つのだった。提案者は、例によって巽だ。
「あ。これだけ騒いだら、先生たちにばれるかな?」
「大丈夫です。細かいことを気にする先生方は、今頃夢の中ですから」
今更の巽の疑問に、明月が先ほどまでとは違った種類の笑みを浮かべて応える。巽とルイスは、ちらりと互いに目線を交わして、明月とは少し距離を取る。
「・・・薬、盛ったのかな」
「・・・だろうな」
「・・・これって、ばれたら余計怒られない?」
「・・・ああ。ま、いつものことだけどな」
「あ、そっか」
「何が『そう』なんですか?」
背後から声をかけられた二人は、後ろめたくもないのに、何故か大袈裟なほどに首を振った。
「な、なんでもないよ。な、ルイス?」
「ああ、気にするようなことじゃないって」
「そうですか」
明月は、肩をすくめて窓へと向き直った。
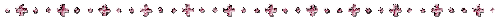
西塔の入り口付近に、人影があった。遠くの東塔のざわめきを背に立ち、準備運動をするかのように、底に適度な厚みのある靴を踏みしめる。
塔の頂上を見上げたのは、ゴーグル越しにも判る、挑むような瞳をした少女だった。長めの前髪が、ゴーグルの上にかかっている。
「ったく。親父殿ってば、厄介なとこにばっかしかけるんだから」
そうした愚痴をこぼすと、少女はおむろに、西塔の城壁に模した壁を登り始めた。
「折角の聖夜だってのに。何が悲しくて、こんなとこ登らなきゃならないのよ」
少女の呟きは、冬の寒風に紛れていった。
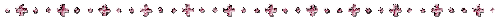
「――のに、まだ聞こえるんだよ。だぁしてぇくれぇぇ・・・って」
話し終えた巽が、ろうそくの炎に照らされた他の二人を見ると、ルイスはともかく、明月の顔がひきつっている。意外にも、苦手なのだ。調子にのって続けようとすると、ルイスがそれを遮った。
不服そうに睨んだ巽だったが、様子が違うのに気付いて、大人しく口をつぐむ。しんとした中に、風とは違って、一定のリズムを持った音がした。
「この音は・・・」
「ああ。外だ」
「いや、何の音?」
ルイスが無言で崩れ落ち、明月が溜息をつく。ついさっきまでの真剣な空気は、一掃されてしまった。巽だけが、きょとんと二人を見やっている。
「おーまーえーなっ」
「なんだよ、だって、わかんないんだから仕方ないだろっ」
「俺たちがいつもやってるだろ!」
「・・・飯でも食ってんの?」
「どこのどいつがどんな食べ方すれば、あんな音が出るんだ!」
「誰かが外の壁を登ってるんですよ」
ようやく巽が納得して、脱力したルイスを残して小声の会話が打ち切られた。揃って、外の音に耳を澄ます。
――にぎやかに吹き荒れる風の音が、聞こえる。塔の内にこもった音は、獣の咆哮めいていた。それに紛れて小さく、石をこするような音。明月が指摘した通り、誰かが外から塔を昇っているのだ。
普通なら聞き逃すところだが、ルイスは耳がいい。他の二人に言わせれば、「ただの地獄耳」ということだが。
とにかくその音は、徐々に近付いてきて、一旦消えた。三人ともが無言で、各々中の興奮を押し留めながら、使われていない暖炉に向かった。自然と、忍び足になっている。
そこは、巽が「サンタクロウスが来るならここ」と目していたところだった。
「俺の勝ち! 明日の昼ご飯、ルイスのおごりだからな」
「甘い。泥棒だったらお前のおごり。ついでに、捕り物劇でニュース出演」
「その場合、怒られるのと褒められるのと、どっちでしょうね」
「・・・ったあ―・・・腰痛ー・・・え?」
静かに騒ぐ三人が出会ったのは、赤毛の、濃いゴーグルをかけた少女だった。
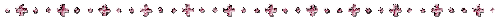
「ついてこないでってば」
「だって、ひまなんだもん」
「閑って、聖夜祭に出れば良いでしょ。今頃盛り上がってるんじゃない?」
「あんな子供騙し、つまんないんだよなー。お菓子とジュースしか出ないし」
「え? 俺結構好きだけど?」
「お前は別。精神年齢ガキだから」
「なんでだよ!」
口の減らない二人の傍らで、七月は額に手をやった。すると、七月とは対照的に、笑顔で二人を見ていた眼鏡の少年と目が合った。
「お疲れですか?」
「あんたたちのおかげでね」
「御愁傷様です」
「使うところ違うから、それ」
深深と、溜息をつく。
まさか、初等部の寮に、聖夜に居残る物好きがいるとは思ってもみなかった。七月自身、五年ほど前には似たような宿舎にいたが、もっと単純に聖夜祭を楽しんでいたと思う。多少いたずらはしたものの、学校を挙げての祭りを蹴ってまで、存在の疑わしい「サンタクロウス」を見ようなどとは、考えなかった。断じて。
そう考えると、なんだか、自分はそう手のかからなかった子供だったのではないかと思えてくる。――大きな錯覚なのだが。
「ところで、どこへ向かってるんですか?」
「んー、ちょっとてっぺんにね」
「何があるんですか?」
「あの狸親父が・・・って、あたし今なに言った?」
考え事をしていると、無防備になる。我に返った七月は、自分の癖を思い出して蒼褪めた。それでなくても、あと少しで目的の頂上に出そうだというのに。
「なあ巽、タヌキオヤジって?」
「狸みたいな親父だろ?」
「まんまだろ、それ!」
「たしか、狸は食えない人とかだったような・・・」
「人なんて美味いのか?」
「意味が違います」
いつからか、話を聞いていた二人が無自覚に茶々を入れる。「自分の言語くらい理解してろよ」という言葉が聞こえ、七月は再び深深と溜息をついた。――こいつらの先生って、大変だろうなあ。
「塔のてっぺんにある、親父の忘れ物を取りに行くだけ。これで満足した? ちなみに、君の回答で正解」
眼鏡の少年を指し示して、七月は一番上の小部屋へつながる扉に手を当てた。
『確認シマス。――照合中。――「ナツキ」一致シマシタ』
ピーッ、と高い音を立てて、扉が開いた。七月の後ろには、わくわくしている三人がいたが、自分一人だけが通り抜けてすかさず扉を閉める。
「えーっ!!」
三人の非難の声が聞こえたが、七月は、ほっと安堵の溜息をついたのだった。窓があるから、これでもう、あの三人と顔を合わさずに出ていける。
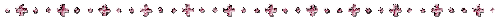
一方の三人は、暗闇の中で顔を見合わせた。ランタンは少女が持っていたため、手元にはなかった。
「・・・どうします?」
「どうって、このまま諦められるかよ?」
「さっき、なんか手ェ当てて・・・」
『確認シマス。――照合中。――不一致デス』
「えーっ、何ソレ!」
「ちょっと、代わって」
『確認シマス。――照合中。――不一致デス』
巽に続いてルイスも呆気なく玉砕し、二人の視線は、ほとんど見えないながらも明月に向かった。明月も、当然のように扉に手を当てた。
『確認シマス。――照合中。――「サンユエ」一致シマシタ』
「!」
先ほどの少女のときと同じように音を立てて開いた扉を前に、三人はまた顔を見合わせた。
「誰、サンユエって?」
「知るか」
「とりあえず、開きましたね」
――「「「やった!」」」
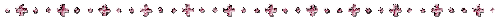
甲高い機械音に、七月は信じられない思いで振り返った。その手には、小さなガラスの容器が握られている。用事は済み、後は出ていくだけのはずだった。
しかし扉は開き、三人が入って来ていた。
「嘘・・・?」
呆気に取られて呟くが、三人は、そんな様子には構わず、小部屋の中を物珍しそうに眺めていた。
「ひどいよ、一人だけ入るなんて」
「それは、邪魔だというのも判りますけどね」
「でもあれはないよなー」
「・・・えーっと・・・訊くけど、あれ開けたの、誰?」
黒髪の小さな少年、眼鏡の少年、金髪の少年と順にランタンを付きつけると、最後の少年がにやりと笑った。
「交換条件。忘れ物って、何?」
やられた、と思うと、可笑しさがこみ上げてきた。本当に、先生たちは大変そうだ。
肩をすくめると、七月は持っているガラス瓶を三人に見えるように持ち上げた。
「これ。見るだけ、触っちゃ駄目よ。毒らしいから、こぼれたら大変」
毒、との言葉に、反射的に金髪の少年と黒髪の少年が身を引き、眼鏡の少年が身を乗り出す。そんな三人の反応に、七月は思わず苦笑した。
「厄介なものばっかり残していってくれたのよ、あの人は。こういう毒や、得体の知れない不老不死の薬とか、呪われてるっていう宝石とか。一覧のリストがあるんだけど、ホント、それ見るとろくな人間じゃないと思うわ」
「どうしてそんなものを、集めるんですか?」
「遺産相続の条件なの。お金は、まあ別に良いんだけどね。あたしのお母さんの遺品とかが、その中に含まれてるから。だから、協力して探そうって決めたのよ、判ってるだけのきょうだい皆で。――で、開けたのは誰?」
揃って顔を見合わせて、眼鏡の少年が軽く手を上げた。
「僕です」
「じゃあ、あなたがサンユエね? 漢数字の三に、月?」
三人は、訝しげに七月を見つめた。違うのか、と呟く。
「ごめん、間違えたみたい。それじゃあ、そういうことだから。誰にも言わないでいてくれると助かる」
「待ってください!」
「――何?」
七月は、ガラスの小瓶を慎重にズボンのポケットに入れ、窓に手をかけたところだった。ランタンは、そもそも寮のものを拝借していたので、部屋の中央に置いている。その体勢で、三人を振り返る。
「僕は、捨て児でした。その・・・元の名前が、三月、ですか?」
「知りたい?」
「――はい」
「どうして? 今の生活は、辛い? 違う自分になりたい?」
窓から手を離すと、眼鏡の少年――三月に向き直った。
少年が、首を振る。他の二人は、黙って、そっと見守っているようだった。
「ただ、知りたいだけです。あなたが知っているのなら、知りたいだけです。そのあとどうするかは・・・考えていません」
「まあ、いいけどね。本当に、後悔しない?」
「・・・多分」
「慎重ね。その方が好きよ、あたしは。――こんなところで会えるとは思ってなかったわ、きょうだいに」
一秒、二秒、三秒。
三拍置いて、小さな少年が、え、と声を漏らした。
「えーっ! 何、なんで? えっ、じゃあ明月、この人と一緒に宝探しするのか?!」
「・・・いや、ちょっと黙ってろ、お前。な?」
「でも、だって! そうなったら、もう明月と遊べないじゃん! やだよそれ!」
思わず、七月は微笑した。それは三月も同じで、どこか、その笑顔はほっとしているように見えた。
少年は、友人たちを見やってから、七月に向き直った。
「この場合、どうなりますか? 僕が何かしなければ不具合がありますか?」
「遺産相続に? ううん、別に。ただ、欲しいなら探すのに加わってもらわないと、やっぱりちょっとね。人数多いから、いろんな意見があるし」
「それなら・・・」
「待った」
金髪の少年が、三月と七月の間に割り入るようにして、挙手した。驚いて、三月ともう一人の少年が見つめる。
「質問。多いって、どのくらい? これは、ただの興味だけど。本題はこっち。――それって、明月一人でやらないと駄目なこと?」
「きょうだいは、全部で十二人・・・の、はず。多分ね」
「多分って?」
「あちこちで子供作って、名前だけつけていったっていう最低男だから。で、順番滅茶苦茶だけど、月の名前でいってる筈だから。ちなみにあたし、漢数字の七に月で、なつき。よろしくね、三月・・・明月って呼んだ方がいい?」
「はい」
にこりと笑う。そこには、迷いは微塵もなかった。
「ええと、それで・・・一人で、ねえ。うーん、別にいいんじゃないかな? 人雇ってるのもいるし。手伝う奴らには、当然遺産は行かないし、何人でやろうと、分配は一人分だけだろうけどね」
何やら、顔を輝かせる三人組に、七月は思わず微笑した。考えが、手に取るようにわかる。きっとこれは、最高の冒険なのだろう。
それでいい。
少しばかり血の繋がったあのきょうだい達は、皆、それぞれの動機に基づいてこんなことをやっているのだから。
「詳しいことが知りたかったら、ここに連絡して。五月って奴。照合のために地下髪の毛でも送れって言われるけど、悪用はされないから。それに、結構話の分かるやつよ」
連絡コードの書いた名刺を渡して、今度は制止の声の挟まれる前に、ひらりと窓から外に出た。
帰りは、ブーツの重力緩衝装置が作動するので、ただ塔の壁面を滑り落ちるだけで良かった。
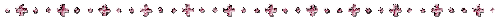
「あー。行っちゃった」
巽が、残念そうに窓から身を乗り出す。
万が一を考えて、ルイスがその服の一端を掴んで、明月の方を向いた。
「さあ、どうする?」
お膳立てはしてやったぜ。
言いもしていない声が聞こえて、明月は、微苦笑した。どうするも何も、決まっている。
「僕と巽はともかく、ルイス、あなたは授業を削った方がいいでしょうね。そうしないと、空き時間ができない」
「んー。じゃあ、構造理論と行政書類削るか。そうすれは、丸一日空くだろ。お前も、栄養素学削っとけ夜」」
「あれは、ビデオ授業とレポートでも大丈夫です」
悪戯を考えるときの様子そのものの二人。
しかしそれも、巽の声に変化する。
「あ! 走ってきた、警備員だ!」
塔は高いが、巽の視力は、大平原で育ったかと思うほどにいい。ルイスと明月は、顔を合わせる間も惜しんで、巽を引っ張って自室へと駆け戻った。
後日、ルイスは構造理論と行政書類書式の授業を辞め、明月は栄養素学に直に出席することはなくなった。そうして、それらの授業のある日、三人で連れ立ってで歩くことが増えたのだった。
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
