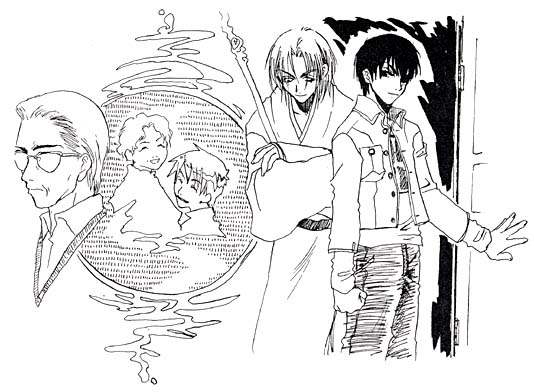
いつもであれば笑い飛ばすような、そんな状況だった。子供ではあるまいし。この歳になって何を言っているのだ、と。だが、それがどうだろう。現に今、人を雇い、自分は部屋の隅で怯えている。なんとも滑稽な光景だ。しかしこれが現実なのだからたちが悪い。
飛び込んだ店では、厭な顔一つせずに引き受けてくれた。もっとも、内心は呆れていたかもしれない、それとも、若者ばかりだから本当に信じてくれたのだろうか。とにかく、その日のうちに榊正義と香坂征と名乗る子が二人来てくれた。今二人は、青色の長細い棒を持って、私の目の前にいる。
「なあ、ロクダイって名前じゃなかったのか」
「お主、知らんかったのか。それは月夜の猫屋の六代目店主だからと彰が呼び始めた名じゃよ」
「彰が。え、猫屋って彰が主じゃなかったのか?」
「名前だけで大した意味はないが、一応わしじゃよ」
「へえ。俺、てっきりロクダイってのが名前だと思ってた」
「そんなわけがなかろう」
「だって、二人が当然みたいにそれで受け答えしてるから・・・」
物音がした。
聞くともなしに二人の会話に耳を傾けていたのだが、聞こえたほんの小さな音に体が強張る。同じく気付いたらしい二人が、目を見交わして音が聞こえた方を見遣る。長い、ねっとりとした時間が流れる。間が重苦しい。
「違うみたいですね」
榊と名乗った方が言う。その前に、香坂が耳打ちしていた。物音くらいでびくびくして、とでも言ったのかもしれない。だが、これが浩次かもしれないと思うとそんなことも気にはしていられない。浩次が、息子が襲ってきた時、この二人は頼りになるのだろうか。
今度は無言で、思い思いに椅子に腰掛ける二人を覗う。榊は高校生くらい、香坂はそれよりはわずかに年長だろうか。香坂が着崩してはいるが着物を着、言葉が時代がかっているという以外には変わったところのない青年たちだ。手足も細く、贅肉はなさそうだが特に力があるようにも見えない。棒を手放さず持ってはいるが、あれで浩次に太刀打ちできるのだろうか。いや、それ以前に浩次を見て戦う気を起こすだろうか。そのまま逃げてしまいはしないか。
何故私が、こんな目に遭うのだろうか。男手一つで育てた息子を成人を目前に亡くし、初七日もあけないうちにそれに襲われるなどと。夜道で出会った姿を思い出し、ぞっとする。辛うじて浩次だとわかったが、映画のゾンビのような酷い姿だった。闇に溶け込むようにして、私を襲ってきた。思い出すだけで体が冷たくなる。あんなものが本当にいるとは。よりにもよってそれが自分の息子とは。
「顔色が優れませんよ。何か飲み物でも淹れましょうか」
とてもではないが、そんな気分ではなかった。
「ですが、・・・・ロクダイ」
香坂が立ち上がり、この部屋で唯一の扉に体を向ける。同様に動こうとした榊は、一瞬妙な表情をした。だがそれよりも・・・。
「来おったな。主人、そこを動くでないぞ」
扉の向こうから、黄土色の顔が現れる。辛うじてそれとわかる、息子の姿だった。浩次は、私を憎んでいるのだろうか。博美のように。無意識に、足が浩次へ向いた。
「畑中さん!」
「セイギ、そっちは頼むぞ」
「ああ。へまするなよ」
「わしを誰だと思っておる」
堪らなく恐ろしいのに、進むのを止められない。あの子が、浩次が私を呼んでいるのだから。香坂が棒を構え、浩次に対峙する。やめろ・・・・・。浩次をどうするつもりだ。
「行くな。そのために俺達を雇ったんだろう」
榊が、私の邪魔をする。何の権利があって、浩次に会うのを妨害するのか。あいつのときにも間に合わなかった。仕事で出ている間に、一人でひっそりと死んでいた。妻の、博美のときにも、息子のときにも、死に目にさえ会えなかったのだ。だから今、行かなくてはならないのだ。
「あんたが依頼したんだ。行くなよ」
違うんだ。あの時は驚いただけなんだ。本当は、また会えただけでも嬉しかった。一緒に、博美のところにつれて行って欲しかったんだ。憎まれているとわかっていても、また会いたかったんだ。
「待てよ。そんなの駄目だ、それじゃ何にもならない」
何を言っているんだ。私がそれでいいと言っているんだ。ずっとこうなることを望んでいたんだ。浩次が生まれてすぐに、博美が死んでから。ずっと・・・ずっと。
浩次が伸ばした手に届かないうちに、あの子は棒に貫かれた。
全く動かなくなったそれは、死体そのものだった。
「これが、現実じゃよ」
どうして。あの子が来てくれたのに。怒りでも憎しみでもいい、来てくれたのに。ろくに構ってやれなくて、互いに接点がなくて、それでもただ一人の家族。博美が、たった一つ残して行ったもの。来てくれたのに。あの子が・・・来てくれたのに・・・。
「いいかげん、解放してやるんじゃな。お主も、家族も」
意外に穏やかな瞳が私を見ている。浩次と同じくらいの年齢のはずなのに、私よりも歳を重ねたかのように見えた。着物と言葉遣いに違和感がないことに、初めて気付いた。
「いつまでもひとところに留まることは叶わぬよ。休むのは勝手じゃが、いつかは進まねばならん。それとも、しがみついていることが最善と思っておるのか?」「歩き出せよ。ゆっくりでいいんだ。あんたは、歩けるんだから。生きてるんだから」
ただ、一般論を口にしているようには聞こえない。息子と同年代の若者に説教され、それがこんなにもこたえるとは考えもしなかった。まさか、避けていたことに真っ向から向かわされるなど。後悔したまま過ごし、素直に認めることも出来なくなっていたことを、こんな風に示されるなど。
「お主はもう気付いているはずじゃ。囚われておったのはお主の方じゃよ。さて、わしらはそろそろ失礼しようか」
私を見る二人の眼は、優しいものだった。この人達は一体・・。
「行くぞ、セイギ」
「ああ」
そうして、変わった二人は出ていってしまった。私は、その最後の言葉に救われた。
「二人は、あんたを恨んでなんかなかったぜ」
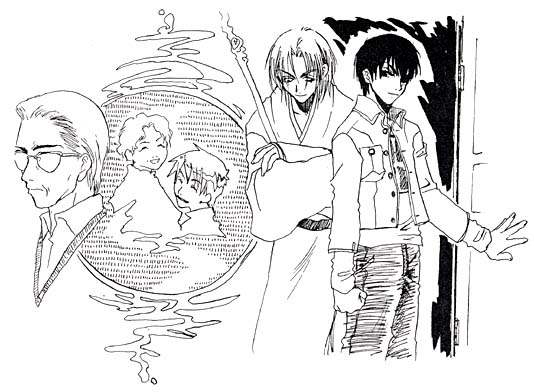
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
